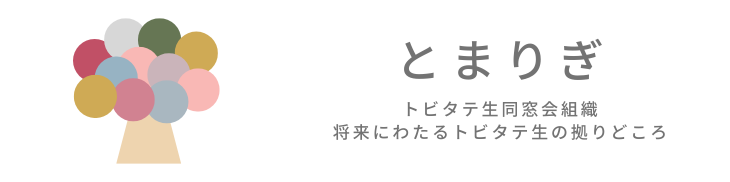【再掲載】第16回:堀佳月さん(多様性人材コース 6期生)
なぜ、「自分らしくいられる教室作り」というテーマで 留学しようと思ったのですか?
堀) きっかけは、一つの映画。大学4年生の時に見た『HAFU -ハーフ-』というドキュメンタリー 映画です。その映画では「日本×○○」というハーフの人たちが抱える葛藤が描かれてたんだ よね。世間一般の認識ではハーフというだけで「かっこいい」「かわいい」「バイリンガル」 などのイメージが付きがちなんだけど、日本に住む彼らの葛藤を見て、将来教員になる自分が 担任となるときに、どのような事が想定されるか考えた。文化と文化の間にいるハーフの子供 たちをどうやって支えていくかということにすごく興味を持った!
幡谷) なるほど。グローバル化進んでいく世界で、そういった環境はますます増えていくかもね。
堀) もう一つ理由があって、それは私自身もハーフだということ。実際この映画を見るまで、自分 のアイデンティティについて考えたことはなかったんだけど、急に向き合ってこなかったこと に後悔を覚えたんだよね。「ハーフとしてどういう人であれば良いのだろう」ということを時 間をかけて勉強したいとも感じた。 きっと、自分のアイデンティティに向き合う時間を増やすことで、その経験がマイノリティで あるハーフの子供たちに真に向き合える様な教員になれると考えた。
現地での活動で心に残ったことってありますか?
堀) 私自身の留学のきっかけは『HAFU』という映画からであって、多様性ということは、人種や 言語の違いだと感じていたの。だけどカナダではそういった概念に収まらなくて、もっと広い 考え方だった。具体的にはね、「社会格差とか経済格差の中で教育はどういう様に機能するか」 とか「LGBTQの人々の立場」とかかな。どの国の子供とか、言語の違いというラベルで多様 性を捉えようとしていたのだけれども、子供たちをアセスメントする視点って限りなく無限に 近いんだなという気づき、教育者としての新しい視点を貰えたかな。

留学後の進路について
幡谷) その留学から、院進学に踏み切った理由とかは留学と繋がってたりするのかな??
堀) そうだね、現地の大学に行って同世代の教員養成課程の人と授業を受けられたことが大きな理 由だと思う。とりわけ教育哲学の授業が印象に残ってるかな。いわゆる「教えるとはなんぞや」 「学ぶとはなんぞや」的なね。その事について深くディスカッションして、教育に対する信念 をみんながぶつけてくる事で、自分の見解が圧倒的に足りてないことを感じた。自分の意見に 対して、「なんで」と深めていく姿勢は日本の授業では得られなかったかな。 だからこそ、教育というものをより深く知りたいという動機になっていったのかな。
堀) もう一つ院進学したい理由がある。結局私がカナダに行って経験してきたものって、日本での 環境では完全に再現はできないんだよね。日本はアジアの影響を受けて村社会的な発展をして 来たけど、カナダはフロンティアマインドで発展して来たわけだし。カナダで学んだことをど うやって日本でアウトプットしていこうかと考えたときに、日本の現場自体をそんなに知らな いとも考えた。だから大学院では、実践にもよりフォーカスした活動をしていきたいよね。
幡谷) 確かにね。やっぱりアウトプットする事で自分の能力になるもんね。
実は悩みもあって・・・。
堀) 最近すごい困ってることがあって、、、。先生ってすごい難しいなって。
幡谷) というと??どう難しいの??
堀) いい意味でも悪い意味でも、先生は影響力を持ってる。先生のやってることを見て、子供たち はどうなりたいかというマインドを形成していくから。私は、子供たちに固定観念を作りたく なくて、私たちが大人がやっていることが全てじゃないし。トビタテの船橋さんも良く「大人 を疑え」と言っているじゃん。
幡谷) 確かに、そうだね。
堀) 職業としては何かしらの手解きはすべきだけど、一方で私の真似はして欲しくないし、周りに あるものは教材として使っているだけでそれ自体をそのまま踏襲して欲しくはない。
幡谷) でも、教員によっては逆に「このレールを行きなさい」みたいなことを言う人もいるんじゃな いかな。
堀) そうだね。とりわけ進路の話になるとそれはあるかもね。
幡谷) 実際現場に立ったら、そういう先生ともやっていかなきゃいけないんだろうね。
堀) もちろん、そういうのも必要な時もあるけどね。「はーい、自由にやりなさーい」で子供たち を放ったらかしにはできないし。急には考えられないから、彼らのガイドとなるべき時も必要 だね。それを如何に子供たち主体で考えさせるかってところが重要なんじゃないかな。

今後の展望
幡谷) 今後の展望としては、ひとまず教員になるって所なんだよね?
堀) そうだね。でも、教員で人生を終わらせるつもりはない。
幡谷) お~、やはりそうだよね。
堀) 全くそれは考えてなくて、私が最終的に行きつきたい所は、外国にルーツのあるとかマイノリ ティである子供たちが学校の中でも、偏見なく自分らしくいられる学校づくりをしたい。それ は私一人では成し得ないことだから、協力者を集めて教育委員会に行くだとか、先生同士のコ ミュニティを立ち上げてプロジェクトを立ち上げていきたいんだ!なんかそういうことを、自 分がやらなきゃいけないんだ!っていうことを感じてるんだよね。
幡谷) なるほどね。なんか天命を授かったような感じだよね。
堀) でも、それに関して何もプレッシャーを感じていないし、その事があるからこそ、エンパワメ ントされているかな。 だから今は、いろんな人に会って仲間を集めたい時でもあるかな。将来のためにね。
そこまで自分を突き動かす信念とは?
堀) そうだね、私が人として大事にしていることは「人をラベル付けしない」ってことかな。これ に尽きる!トロントでの経験のなかで一番自分が変わったこと。みんな見た目違うし、話して る言語も違う、普通にセクシャルマイノリティーもいる。でも、この人は「○○」だからみた いなレッテル貼りが本当に無駄だと感じた1年半の留学だった。一応私は日中ハーフだけど、 とある先生に中国人と間違われて冷たい態度を取られていたんだけど、いざ日本から来た人だ と分かるとすぐに手のひら返して態度変えてきて、そこがすごく気持ち悪く感じた。目の前に いる私は何も変わってないんだよ。「私」としてここに居るのに、人種って概念で態度変えら れるの「なんなんだろう」って思った。でもその時、自分を振り返った時に自分もそういうこ とした事あるんじゃないかと気付いた。それからは、子どもであってもあまり子ども扱いはし ないっていう意識を持って接するようにしてる。子どもの一意見として、ちゃんと向き合うよ うにしてる。だからトロントの人たちが「なんで?」と深掘りしているのかという意味が分かっ た。一人一人バックグラウンドが違うから、どういう経験から相手の意見に至るのかも違うし、 考え方の軸も違う。そういった価値観を大事にしていきたいんだ。
幡谷) 確かにね。僕もヨルダンで人種差別的な事受けてきたし、なんか分かるな。 世の中的には、まだまだレッテル貼してしまう人の方が多いのだろうね。トビタテというコミュ ニティに入ってしまうとそんな事、自然としなくなるんだろうけどね。
堀) そうだね。レッテルを貼っちゃうと、素敵な出会いを見過ごしてしまう可能性が高いよね。 本当のコミュニケーションにラベルは要らない。ラベルじゃなくて、「その人」を見ないと。
幡谷) そう考えられただけでも素晴らしい留学の成果だね。素敵な話をありがとうございました!
編集後記 堀さんとの出会いは、およそ半年前のトビタテ関連イベントでした。その時、教育という軸を持っ て熱く意見を言う姿を覚えています。偶然にも当時茨城県の方に在住という事で、私の出身でし た。私の発案で茨城県内の高校生に向けたイベントの際はお手伝いしていただけたり、逆に彼女 が主催のイベントに参加したりと交流は割と多かったです。ただ、留学そのものや経験自体を深 く聞いた事はなかったので、今回のインタビューを通して私としても色々な気づきを得られたも のとなりました。仲間の近況を聞くこともでき、モチベーションが上がった1日となりました。大 変ありがとうございました。